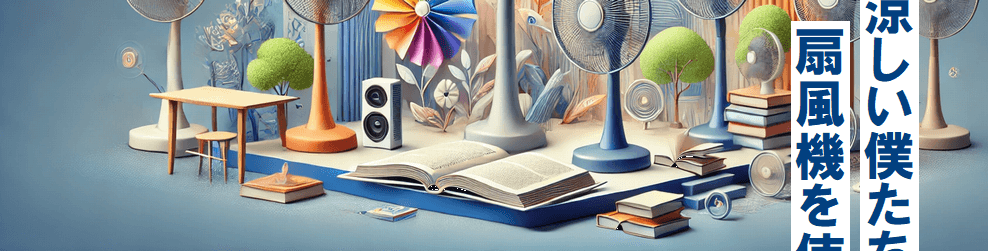2024/12/18
「広島には100台だってよ。」
敷島が嬉しそうに言った。その場にいる男たちもみな嬉しそうに聞いていた。
それもそのはず。広島の社会全体が大型扇風機のない世界線に移動してしまって半年。もう今は5月も末だ。まもなく始まる暑く長い夏に備えて大型扇風機は必須の家電だ。
「……で、どうやって持ってくるんだ?」と、長谷川が口を開いた。
「トラックだよ、もちろん。竹原からこっちへ陸路で持ってくるルートは、まだ使える。」
「いや、そうじゃない。検問はどうする?あいつら、電気製品には目を光らせてるって話じゃないか。」
敷島は黙った。確かに問題はそこだった。半年も前、”切断”が起きた日から、電力の使い方に対する統制は強まり、許可のない家電はすべて「回収対象」とされている。
「……偽物に偽装するしかないな。」と、誰かがぽつりと呟いた。
「偽物?」
「うん。中身をそっくりそのまま抜いて、木枠にでも詰めて『美術品』ってことにすれば、検問は通せるかもしれない。」
「それでバレなきゃいいけどな……」長谷川が言った。
沈黙が流れた。誰もが、今年の夏が普通では済まないことを分かっていた。広島の気候は昔から湿度が高く、風がなければ蒸し焼き同然だ。しかも、移動後のこの世界では、空調の代替技術も満足に機能しない。
「……とにかく、100台ある。これを手に入れれば、俺たちはこの町で“風を持つ者”になれるんだ。」
敷島のその言葉に、再び静かな熱が灯る。
彼らの目には、ただの家電以上のものが映っていた。
それは、支配された空気に風穴を開ける自由の象徴だった。
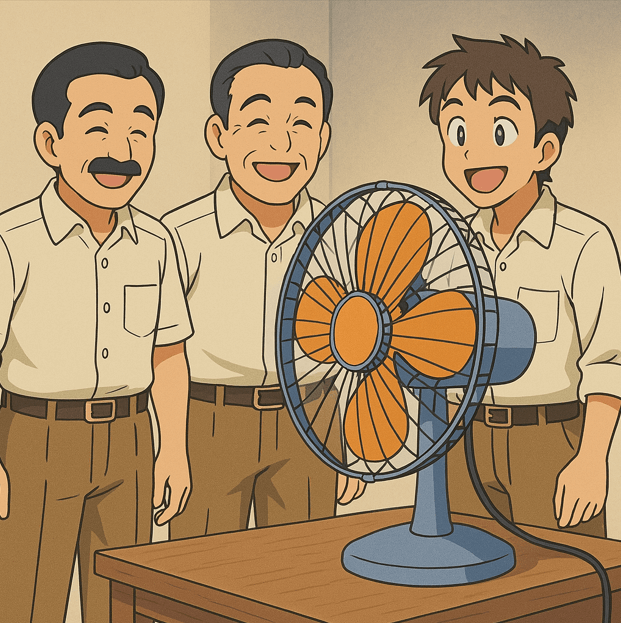
トラックが竹原を出たのは、6月1日の夜明け前だった。
運転するのは敷島の従兄弟で元・運送業者の笠木。荷台には100台の大型扇風機が積まれていた。ただし外見は、どれも古びた美術彫刻や設計模型のように見える。カバーを被せ、錆加工まで施した「偽装」だ。
検問所は廃線になった駅の近くに設けられていた。重装備の係官たちは手慣れた様子でトラックに近づいたが、笠木は落ち着いていた。荷台をちらと覗いた係官の一人が「これは?」と聞いたときも、
「県立大学の展示品っすよ」と、即答した。
「中、開けても?」
「どうぞ。崩れやすいんで、気をつけてくださいね。」
係官たちはしばらくボソボソと相談し、二つのカバーをめくったが、内部には確かに「美術作品」のような姿をした何かが見えた。中身までは調べなかった。
「……通っていい。」
それだけ言って、トラックは再び走り出した。
町に100台の扇風機が届いたのは、その翌日の夜だった。
搬入は手分けして行われ、闇のなかで音を立てないよう注意された。
電力網に直接つなげば即座にバレるため、彼らは旧い手動発電システムを併設した。かつて戦時中に用いられていた足踏み式のものだ。
子どもたちが交代でペダルを踏み、大人たちは風にあたる。笑い声が、何ヶ月ぶりかに路地裏に戻ってきた。
町の人々はそれを「夜の風」と呼んだ。
けれど、事態は長くは続かなかった。
6月15日。中央からの電力管理局が抜き打ちの調査にやってきた。町の電力使用量が「不自然に安定している」ことに疑問を持ったのだ。調査は厳しかった。家々の中をくまなく見て回り、物陰を、床下を、屋根裏を調べた。
そして、1台。納屋の裏に隠されていた扇風機が見つかった。
「お前たちは知っていたのか?」
管理局の男がそう言ったとき、敷島は前に出た。
「俺たちは暑さに耐えられなかった。それだけだ。」
「それは法の下では理由にならん。」
「そうかもな。でも、あんたらが風を奪ったんだ。なら、俺たちはそれを取り戻す。」
管理局の男は何も言わなかった。ただ静かに、その場にいた人々の顔を見回した。
「罰則は本来、全体停電処分だが……今回は見逃す。条件がある。」
「……なんだ?」
「この風を、他の町にも分けろ。」
その年の夏、広島には各地で「夜の風」が吹いた。
100台の扇風機は、ある町から次の町へと巡回し、どこでも子どもたちがペダルを踏み、年寄りたちが昔話を語り、若者たちが自由の匂いに笑った。
電力が統制されても、風は統制できなかった。
そうして、風は再び、人の手で生まれはじめた。
社会が失ったものは、やがて人の力で取り戻される。
その始まりが、100台の扇風機だった。
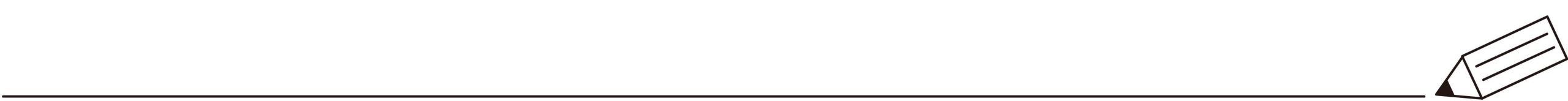
編集後記:
人は、風ひとつにも意味を見出す生き物です。
この物語は、単なる「扇風機」の話ではありません。
奪われたものを、自分たちの手で取り戻そうとする小さな町の人々の記録です。
それはたとえば、音のない夜にそっと立つ風のように、目立たずとも確かにそこにある“意思”の話でもあります。
私たちが日々当たり前のように享受している「快適さ」は、
いつか突然、その理由も分からぬまま消えるかもしれません。
そしてそのときこそ、人の知恵とつながりが試されるのでしょう。
「風を持つ者たち」が描いたのは、まさにそうした未来に対する希望です。
発電機を踏み続ける子どもたち、身を挺して風を運んだ男たち、
そしてそれを受け取った町の人々——誰もが名もなきヒーローでした。
読んでくださった皆さんが、この物語の中に、
自分の暮らしや、失いたくないものを少しでも重ねてくれたなら、
それ以上の喜びはありません。
次に風が吹くとき、あなたの胸にこの物語がそっと蘇ることを願って。