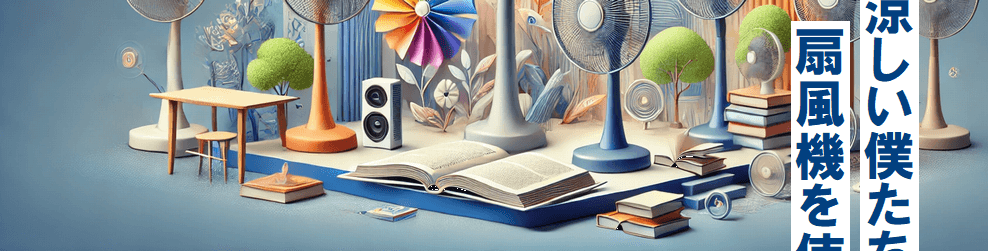2024/12/18
電気が無くなった世界では、どんな些細なエネルギーでも無駄にできない。ハイブリッド扇風機や蒸気機関式の巨大ファンに限らず、日常生活全般が「工夫」と「協力」によって成り立っていた。扇風機一つ動かすのにも、必要な部品の製造、燃料や水の確保、メンテナンス要員の配置など、かつては考えもしなかった手間がかかる。だが、その労力を分かち合う人々の間には、かつての電気が支配していた世界では得られなかった連帯感や喜びが生まれていた。
タクミのコミュニティでも夏が近づくにつれ、「どうやって涼を確保するか」が毎年の議題になる。ハイブリッド扇風機は普及が進み、住民たちの生活の支えとなっていた。風が吹く日は自然に任せ、吹かない日はハンドルやペダルを漕いで羽根を回す。疲れたら誰かと交代する。ついでにおしゃべりを楽しんだり、子どもたちが遊び感覚でハンドルを回してくれたりするのだ。昔の世界なら、ただ電源を入れるだけで風が得られた。しかし今は「何もしないと風は得られない」代わりに、「労力をかけると確実に風が吹く」という手応えがある。それは不便のようでいて、人の心を豊かにする不思議な感覚を伴っていた。
家庭内では、ハイブリッド扇風機が人々の会話の中心になったりもする。「今日は私がハンドルを回す番ね」「よし、じゃあ俺はペダルを漕ぐか」そんなやりとりが家族や友人たちとの時間を増やし、コミュニケーションのきっかけを作る。一緒に風を生み出す行為が、自然と笑顔を誘うのだ。かつての社会では、エアコンの効いた部屋でそれぞれがスマートフォンの画面を覗き込み、同じ空間にいながら会話がないことも珍しくなかった。しかし今は、流れ落ちる汗を拭いながら「少しでも涼しくなろう」と手を動かし、声を掛け合う。電気に頼る便利さが失われた分だけ、家族や仲間が持つ結束力が強まったように思われた。
タクミはそんな光景を眺めながら、「電気」という存在が自分たちに与えてくれた恩恵と同時に、「人の体の力」や「自然の力」と向き合うことの大切さを改めて感じていた。もしも再び電気が復旧する日が来たとしても、人々はもう忘れないだろう。「涼しさ」ひとつ取っても、これほどまでに多くの工夫や努力が必要なのだと。その尊さを知ったからこそ、以前のように当たり前に消費するだけの生活には戻れないだろうと予感していた。
そして、タクミはまた新たな目標を胸に抱いていた。小型の発電機を搭載し、夜間の灯りや簡易充電ができるハイブリッド扇風機の開発。蒸気機関の技術を応用したより効率の良いファンシステムの研究。さらに、コミュニティ同士を繋ぐ情報交換の場をつくり、世界中の人々が発明や知恵をシェアできるようにすること。電気が無くとも、アイデアや知識を伝える手段さえあれば、人々は想像以上に多くのことを成し遂げられるはずだ。
大停電から数年が経過し、電力インフラが元通りに復活する兆しはまだ見えていない。しかし、かつての世界と比べて必ずしも暗い未来ばかりではないと、タクミは思うようになった。人々は汗をかき、体を動かし、そして自然の力を借りて、確実に「風」を起こしている。それは、涼を得るという単純な目的だけではなく、人間が自らの手で未来を切り開いていくための“象徴”でもあった。いつか、また新しい形の文明が開花するとき、扇風機という身近な装置がその鍵のひとつになり得るのかもしれない。少なくとも、タクミと彼の仲間たちの目には、その可能性が確かに輝いていた。
今日も夏の日差しが厳しい。コミュニティの中央広場では、ハイブリッド扇風機の試作機が規則正しいリズムで羽根を回転させている。誰かがハンドルを握り、また別の誰かが笑顔でペダルを漕ぎ始める。風はそよそよと人々の間を駆け抜け、暑さをほんの少しやわらげる。そんな姿を眺めながら、人々はもう一度だけ、力を込めてハンドルを回し続けるだろう。そこに生まれるのは、ただの涼しさだけではない。人と人との繋がりと、自然への畏敬の念、そして明日への希望が入り混じった新しい風が吹いていた。
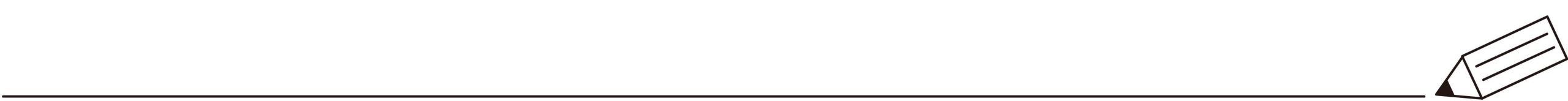
編集後記
本作では、電気がなくなった世界で人々がどのように「風を起こす」かを軸に、技術文明の後退と再生の可能性を描いてきました。涼を得るための手段として、自然エネルギーと人力を組み合わせたハイブリッド扇風機や、コミュニティ単位で稼働する蒸気機関式の巨大ファンなど、さまざまなアイデアが生み出され、試行錯誤を繰り返す様は、ある種の“人間のたくましさ”を体現しているように思います。
電気が当たり前に利用できる現代において、扇風機はスイッチを押せばすぐに風を得られる便利な道具です。しかし、それがある日突然、誰の手にも届かなくなったとしたら――。見えないところで支えられていた文明の複雑さと、“当たり前”がどれほど貴重な恵みであったのかを思い知ることになるでしょう。本作は、その“当たり前”を失った世界だからこそ、人と人が協力し合う場が生まれ、日常のあらゆる所作が改めて考え直される様子を浮き彫りにしています。
地道な手間や工夫を共有することで、社会は一歩ずつ前へ進む。扇風機が「涼しさ」を届けるだけの装置にとどまらず、人々が互いに手を携えて未来へ向かう“象徴”としても描かれているのが、この作品ならではの特徴です。ある人はハンドルを回し、またある人はペダルを漕ぎ、蒸気機関を維持するために薪を集め、水を管理する。見過ごされがちな作業や行動が、思わぬコミュニケーションのきっかけになったり、人間同士の温かいつながりを育てたりする。それは、自分自身で風を起こすことで感じる“生きている実感”でもあります。
もちろん、実際にこのような大停電が起きる可能性は決して無視できるものではありません。頻発する自然災害や未知の脅威を考えれば、本作の世界はありえない未来ではなく、一つの警鐘としても読めるはずです。だからこそ、私たちがいま享受している文明の恩恵を振り返りつつ、万が一それを失ったとしても前向きに生き抜くための糧として、新しい暮らしのヒントを見出していただければと思います。
最後まで読んでくださった皆さまに、心からの感謝を申し上げます。もし本作のストーリーが少しでも想像力を刺激し、“電気がなくても人は生きていける、そして互いを支え合うことでより豊かな関係が築けるのではないか”という気づきや感慨をもたらせたのならば、これほど嬉しいことはありません。電気にあふれた日常へと帰るそのときも、「自分の力で風を起こす」という感覚を決して忘れずにいたい――。その思いが、この作品の編集後記として、皆さまの心に残っていただけたら幸いです。